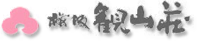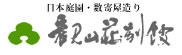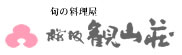どうして端午の節句に、ちまきを食べるの?
……と、小学生の甥からこの間、聞かれました。
即答できず、「そ、そういうことは自分でまず調べなさい」と
とりあえずはかわし、早速本を紐解いてみると。
話は今から約2300年前の中国に戻ります。当時、屈原という
詩人が国王の側近として仕えていました。屈原は正義感が強く
国民からも大変慕われていたそうですが、陰謀によって失脚し
国を追われてしまいます。
絶望した屈原は、川に身を投げて自殺。その日が5月5日だったそうです。
屈原の死を悲しんだ国民は、たくさんのちまきを川に投げて弔いました。
ところが漢の時代に、里の者が川のほとりで屈原の幽霊に出会います。
幽霊曰く、「里の者が毎年供物を捧げてくれるのは有り難いが、残念なことに、私の手許に届く前に蛟龍(こうりゅう)という悪龍に盗まれてしまう。だから、今度からは蛟龍が苦手にしている楝樹(れんじゅ)の葉で米を包み、五色の糸で縛ってほしい」と言いました。
それ以来、楝樹(れんじゅ)の葉で米を包み五色の糸で縛って川へ流したので、無事に屈原の元へ供物が届くようになりました。
これがちまきの始まりと言われています。屈原の故事から、中国では五月五日の節句には、節物としてちまきを作り、親戚や知人に配るという習わしが生まれました。
そして、その風習は、病気や災厄(さいやく)を除ける大切な宮中行事、端午の節句となったと言われています。時が流れて後、中国の三国志の時代、端午の節句は、魏(ぎ)の国により旧暦五月五日に定められ、やがて日本にも伝わってきたというわけです。
……まさしくちまきに歴史ありですね。
ところで、桜坂観山荘では、端午の節句お祝いプランを実施中です。
おかげさまで例年多くのお客様に来ていただいていますが、夜のお席なら
まだ少し余裕があります。
ぜひこの機会に、桜坂観山荘においでください。